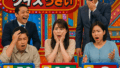「上司がマウントを取ってきてうざい…」そう感じる瞬間が増えていませんか?仕事中なのに過去の武勇伝を聞かされたり、指示が威圧的だったり、自分より下に見られているような言動が続くと、心がすり減ってしまいます。実際、多くの人がマウント上司に悩まされており、それは決してあなただけではありません。
この記事では、職場によくいるマウント上司の特徴を具体例とともに紹介し、その心理や背景をわかりやすく解説します。また、感情をすり減らさないための実践的な対応策や、環境が改善しない場合の選択肢についても触れています。今感じているモヤモヤを少しでも軽くしたい方は、ぜひ読み進めてみてください。
「上司 マウント うざい」と感じるのは普通?|共感とリアルな実態

職場に潜む“マウント上司”の実例とは?
「そんなことも知らないの?」「俺が若い頃はもっと苦労したよ」——こうしたセリフに、うんざりした経験はありませんか?職場には、さりげなく自分の優位性を誇示してくる“マウント上司”が意外と多く存在しています。
例えば、30代女性の営業職の方は、毎日の朝礼で必ず上司の「俺の成功体験」を10分以上聞かされていたそうです。内容は業績とは無関係の武勇伝ばかりで、チームのモチベーションは低下する一方でした。
こうしたマウント上司の問題点は、表面的には「コミュニケーション」として扱われがちな点です。本人は善意のつもりで話しているかもしれませんが、受け手側の心にはストレスが積もっていきます。
仕事の本質から逸れた優位性アピールが続けば、部下は無力感や無価値感に襲われ、次第に仕事への意欲も奪われていきます。
うざいと感じる人が圧倒的に多い理由【実態調査の引用あり】
「上司がうざい」と感じる人は、実は少数派ではありません。あるビジネス系調査会社が2023年に実施したアンケートによると、「職場の人間関係で最もストレスを感じる相手」として、46.8%の人が「上司」と回答しています。
この背景には、以下のような心理的要因が関係しています。
- 反論しづらい立場にあること
- 理不尽な言動に耐える場面が多いこと
- 感情を押し殺して接する必要があること
特に「マウント型」の上司は、こうしたストレスの火種になりやすいです。仕事の成果ではなく“自分のプライド”を守るために部下を押さえつける行動が繰り返されると、部下の精神的疲労は極端に高まります。
「ただの指導」と「マウント」の違いとは?
一見、部下への“注意”や“指導”に見える言動でも、実はそれがマウントであることは珍しくありません。両者の違いは、以下のように整理できます。
| 種類 | 意図 | 言葉の使い方 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 正しい指導 | 成長を促す | 理由や背景を丁寧に説明する | 部下が納得・前向きになる |
| マウント | 優位を示す | 否定や威圧的な言葉が中心 | 部下が萎縮・無気力になる |
たとえば、「このやり方には理由があるから、覚えておいてね」という説明は指導ですが、「そんなやり方じゃ通用しないぞ。俺のやり方を見習え」と言うのは明確なマウントです。
どんな言い方であれ、受け手が「否定された」と感じると、それはすでにマウントの領域に入っていると考えていいでしょう。
マウントを取ってくる上司の特徴7選|あなたの上司も当てはまる?

「俺の若い頃は…」が口癖の自慢型上司
「俺の頃は月100時間の残業が当たり前だった」などと語る上司は、典型的な“過去自慢”型です。このタイプは、過去の苦労を美化して現在の部下に押し付けてくる傾向があります。
自慢が目的なので、現代の働き方改革や効率化には無関心です。部下の努力や成果に対するリスペクトが欠けており、部下のやる気を削ぐ原因となります。
話を聞かない、否定から入る“支配型上司”
部下の意見を最後まで聞かずに「ダメだ」「それは違う」と即座に否定するタイプです。この上司は、常に自分が正しいと思い込み、他人の考えを認める余地がありません。
会話が成立しないため、部下は次第に意見を言うことすら諦めてしまいます。組織内の風通しも悪くなり、チーム全体のパフォーマンス低下につながります。
気分屋+プライド高い=最強にうざい組み合わせ
機嫌の良し悪しで態度が激変する上司は、職場に不安定さをもたらします。さらにプライドが高いとなると、指摘も通じず、間違いを認めないため始末に負えません。
このタイプの問題点は、「今日は何を言ったら怒るのか」が予測できず、部下が常に顔色をうかがうようになる点です。精神的な疲弊が蓄積して、最終的には職場を離れる原因にもなります。
嫌味・皮肉で部下をコントロールするタイプ
「よくその程度で満足できるね」「またミス?成長しないなぁ」など、直接的ではないものの、相手を下げる言葉で攻撃してくるのがこのタイプです。
笑顔を交えて言われることも多く、一見すると冗談に聞こえるため、周囲の共感を得にくい傾向があります。しかし受け手にとっては精神的なダメージが大きく、毎日少しずつ心をすり減らしていきます。
LINE既読スルー&深夜指示型|プライベート侵食型
業務外の時間でも連絡を取り続けたり、土日でもLINEで業務指示を送ってきたりするタイプです。既読スルーされるだけでなく、「なんで返事遅いの?」と催促されることもあります。
このタイプは「常に仕事を優先して当然」という価値観を押し付けてくるため、部下の生活リズムを破壊してしまいます。慢性的なストレスや睡眠不足の原因になりやすく、長期的には心身の不調を引き起こす可能性も高まります。
他人を下げて自分を上げる“比較型マウンター”
「○○くんはもっとできてたよ」「前のチームの方が優秀だったな」といった比較発言を繰り返すタイプです。このような言動は、部下のモチベーションを著しく下げます。
誰かと比べて落とされることで、「自分はダメなんだ」という思考が根付いてしまい、自信を喪失する原因になります。建設的なフィードバックではなく、相対的に自分の評価を上げたいだけなので非常に悪質です。
正論マウントで精神的に追い詰める上司
「お前のためを思って言ってる」「社会人なら当然だろう」といった“正論”を盾にして、反論の余地を潰してくるタイプです。表面的には正しい意見なので、反論しづらいのが特徴です。
ただしこのタイプの言動は、部下の個性や事情を一切無視しているため、思いやりが感じられません。納得感が伴わない正論は、ただの圧力であり、部下の心を静かに追い詰めていきます。
「うざい上司」への対応策|実践的に“距離を取る”方法とは

感情をシャットアウト|マウント上司の言葉は“情報”として処理する
マウントを取る上司の発言は、どうしても感情を揺さぶってきます。しかし、その言葉を真正面から受け止めると、ストレスばかりが蓄積してしまいます。そこで有効なのが「言葉を感情ではなく“情報”として処理する」考え方です。
たとえば、「お前のやり方じゃ遅すぎる」と言われたとします。そのまま感情で受け取ると、「自分はダメなんだ」と自己否定につながります。ですが、冷静に「どの部分が遅いのか」「改善点は何か」という情報に変換すれば、建設的に考えられます。
以下のように、実践的に意識を切り替えてみてください。
- 発言の裏にある「事実」だけを抽出する
- 感情を切り離して「自分の仕事改善に使える要素があるか」だけを見る
- 理不尽な場合は「はい」と受け流し、内心は真に受けない
上司の発言に一喜一憂しないためには、“主観をフィルターで遮断”する習慣が必要です。
社内ツール・メールをフル活用して「記録」を残す
マウント型の上司ほど、指示内容がブレたり、過去の発言をなかったことにしがちです。このような状況では「言った」「聞いてない」といった水掛け論に発展する危険があります。
そうならないためにも、社内ツールやメールを使って、やりとりを文章で残しておくことが重要です。これにより、客観的な証拠として使えるだけでなく、自分自身も業務を正確に把握しやすくなります。
おすすめの記録方法は以下のとおりです。
| 手段 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| メール | 指示・報告をテキストで送る | 言質が取れる。検索・保存が容易 |
| チャット | SlackやTeamsでの簡易やり取り | リアルタイムで即時確認が可能 |
| 議事録共有 | 会議後に要点を共有する | 他のメンバーも内容を把握できる |
上司の言動に不安がある場合は、どんな些細な内容でもログとして残しておく癖をつけると安心です。
直属以外の信頼できる先輩や上司を味方につける
マウントを取る上司と1対1で向き合っていると、次第に視野が狭くなり、孤立感が強くなっていきます。だからこそ、直属の上司以外に相談できる相手を確保することが重要です。
たとえば、他部署の先輩や信頼できる上層部の人と定期的にランチをとるだけでも、気持ちがかなり楽になります。「いまこんなことで困っていて…」と具体的な相談をすれば、客観的なアドバイスも得られます。
社内に味方がいると感じられるだけで、精神的な支えになります。以下のような行動をとると、良好な関係を築きやすくなります。
- 挨拶や雑談を少し増やしてみる
- 困っていることを率直に伝える
- お礼や感謝の気持ちは言葉にして伝える
孤独を感じる前に、社内ネットワークを広げる意識が必要です。
メンタルが限界になる前に“反面教師”思考へ切り替え
マウントを取り続ける上司の言動に耐えてばかりいると、心がすり減ってしまいます。そこでおすすめなのが、「この上司を反面教師にしよう」と視点を切り替える方法です。
たとえば、「こんな言い方をされると人は傷つくんだな」と体感できた経験は、今後あなたが誰かをマネジメントする立場になったとき、必ず役立ちます。
反面教師としての活用法は以下の通りです。
- 上司のNG発言をメモしておき、自分は使わないようにする
- 部下との信頼関係構築に活かす
- 上司の行動と自分の反応を振り返り、自己理解を深める
このように視点を変えることで、辛い経験が“成長の糧”になります。無駄な我慢に見える日々も、将来のあなたの強みに変えることができます。
マウントが日常化している環境の危険性と転職という選択肢

マウント上司の下で働き続けると起こる3つのリスク
マウントを日常的に取られる環境は、非常に危険です。放置していると、以下のようなリスクが現実化します。
このようなリスクを避けるには、職場環境に問題があると気づいた段階で、行動を起こす必要があります。
「逃げ」ではなく「自分を守るため」の転職という判断
「転職は逃げ」と思い込んでいませんか?しかし、限界を超えて働き続ける方が、よほど危険です。職場環境は人生の大部分を占めるため、我慢を美徳とする考えは捨てるべきです。
2024年の厚生労働省の調査でも、転職理由の上位に「上司との人間関係の悪化」が含まれており、決して特別な理由ではありません。
大切なのは、自分が今後どう働きたいか、どんな環境なら力を発揮できるかを見つめ直すことです。心身が壊れる前に、冷静な判断で転職を選ぶのは自己責任の一環です。
転職前にやっておきたい社内リサーチとキャリア相談
転職を検討する際には、いきなり辞めるのではなく、事前の準備が成功のカギになります。以下の行動を取っておくと、スムーズに次の一歩を踏み出せます。
| 事前準備 | 内容 |
|---|---|
| 社内情報の整理 | 自分の評価、成果、他部署の雰囲気をチェックする |
| キャリア相談の活用 | 転職エージェントやキャリアカウンセラーに相談する |
| スキルの棚卸し | 自分の強みや実績を見直し、履歴書に反映する |
特にキャリア相談では、第三者から見た自分の市場価値を把握できます。これにより、視野が広がり、「こんな職場ならやっていける」と自信にもつながります。
現職にしがみつくのではなく、「もっと働きやすい場所がある」と信じて、一歩を踏み出す勇気が未来を変えていきます。
まとめ|マウント上司にうんざりしているあなたへ伝えたいこと

“戦わない選択”も立派な自己防衛
マウントを取ってくる上司に真正面からぶつかる必要はありません。むしろ、冷静に状況を見極めて“距離を置く”という選択こそ、今の時代における賢い自己防衛といえます。
「上司の言動が許せない」「いつか見返してやる」と気負うほど、心は消耗していきます。実際、過度なストレスが続くと、頭痛や胃痛、不眠といった体調不良に発展するケースは少なくありません。ある労働組合の調査では、約35%の労働者が「上司との関係が健康に悪影響を与えている」と回答しています。
無理に変えようとせず、“戦わないこと”を選ぶことも、立派な自分自身の守り方です。以下のような対策が、静かに自分を守る一歩になります。
「逃げ」とは違い、これは“自分を大切にする選択”です。正面から戦わなくても、十分に誇れる対応です。
まずは、あなたの心の声に耳を傾けて
マウント上司に日々さらされていると、自分の感情すらわからなくなってしまうことがあります。「これくらい我慢すべきかも」「社会人なんだから当たり前」と思い込んでいませんか?
でも、違和感や疲れ、イライラは心からのサインです。その小さな声を無視し続けると、やがて大きなSOSへと変わります。
まずは、朝起きたときに「仕事に行きたくない」と思っていないか。上司と話す前に「胃が痛い」と感じていないか。自分の反応に素直になることが、心の健康を守る第一歩です。
以下のようなセルフチェックをしてみることをおすすめします。
| 心のチェック項目 | YES / NO |
|---|---|
| 朝の出勤前に気が重くなる | |
| 上司の顔を思い出すとイライラする | |
| 仕事中に集中力が続かない | |
| 眠れない・食欲が落ちたと感じる | |
| 「辞めたい」という気持ちが何度も頭をよぎる |
3つ以上当てはまる場合、すでに心が悲鳴をあげている可能性があります。カウンセラーへの相談や、信頼できる人との会話、転職活動など、少しでも自分の心が楽になる行動を始めてください。
あなたが悪いわけではありません。どんな環境でも、あなた自身の心を守る責任と権利は、あなたにあります。仕事より大切なのは、あなたの健康と未来です。
おすすめ記事